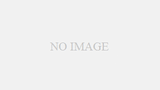◆予期される「不幸の循環」
イスラエルとハマスの停戦合意が発効し、「平穏な生活が戻る」と数万人の避難民がガザ地区北部へと帰還した。数十キロの移動は徒歩が唯一の手段である。しかし、避難民の中には、帰った先の「自宅」の破壊の激しさに衝撃を受け、来た道を戻ってくる人もいる、とアルジャジーラの現地記者が報じていた。 停戦合意には、1日600台の人道支援物資を積んだトラックが入境し、6万戸以上の仮設住宅とテント20万張りが設置されると書かれているが、そのような住宅はまだ1棟も建っていないからである。
この機会を捉えて、米国のトランプ新大統領は 「良い考えがある」として 、ガザ住民100 万人をエジプトやヨルダンなど周辺国に移住させる計画を示唆した。これはすぐに当事国の反対に遭ったようだが、避難民の中には 、爆撃される恐れのない新天地で生活を再建したいと考える人もいるだろう。仮設住宅で生き延びても、そこがコンクリート 造りの新居に変 わったところで再びイスラエル軍に破壊される「不幸の循環」が予期されるからだ。この悪循環を断つ選択を避難民がしても、誰も非難することはできない。しかし、その一方で「ガザこそわが祖国」と移住拒否をする人は必ずいる 。(こちらの方が圧倒的に多いとされる)
◆実現していない戦争目的の達成
このように考えると、ガザ地区で民族浄化を断行し、パレスチナ人を追放して 最終的な安全保障を確保するとのイスラエルの隠れた戦争目的は半ば実現したように見えて 、実は達成できていないのではないか。ハマスは、最後まで抵抗の旗を降ろさなかったとガザ住民の「勝利」を宣言した。
建物の7割が破壊され、家屋の92%が損傷したとされる壊滅的な破壊を受け、4万7000人以上の実際に数えられた死者に加え、なお1万人程度ががれきに埋もれたまま行方不明とされる。この犠牲の大きさを考えれば、それを勝利と呼ぶ狂気に賛同することはできないが、一方で、イスラエルが勝っていないことにも留意すべきである。ネタニヤフ首相が掲げた表向きの戦争目的である 「ハマス殲滅(せんめつ)」は実現せず、「人質引渡し式」には、武装したハマス戦闘員が参列した。
◆さらなる人的犠牲の可能性も
極右勢力のスモトリッチ財政相が、停戦の第2段階でイスラエル軍にガザ地区の完全な再占領を求め、支援物資をハマスから剥奪せよと呼びかけた背景には、このような現実がある。また、イスラエル軍は、ヨルダン川西岸地区での軍事活動を活発化させている。絶対にあってはならないことだが、イスラエル軍がジェノサイド (集団殺戮を再開し、あるいはその矛先をガザ地区から西岸地区に移し、さらなる人的犠牲が積み上がる可能性を警告せざるを得ない。その意味でガザ戦争はまだ終わっていない。
ガザ地区の復興には、膨大な費用と時間がかかる。国連パレスチナ難民救済事業機関 (UNRWA)をはじめとする国際機関や各国政府は支援を申し出ているが、この歴史的に例を見ない大破壊は自然災害ではない。イスラエル政府が意図的に起こした国際法違反の犯罪である。その責任が問われることなく、戦争犯罪が処罰されることもなく物事が進んでいくとすれば、その面でも人類社会は大きな軋轢(あつれき)を経験することだろう。問題は全く解決していない。更なる困難が待ち受けている。