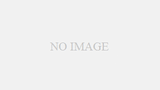◆進行するガザ地区の飢餓
SNS に投稿された一つの写真を前に書いている。やせ細った乳児を抱え、自身も頬がこけ、うつろな目をした母の写真だ。ガザ地区では、国連の総合的食糧安全保障レベル分類(IPC)で最悪とされる段階の飢餓が進行している。そしてそれは、自然災害によるものではない。そうであれば救済はどれほど容易か。世界中の政府、人道機関が用意した救援物資を満載したトラックが、検問所の外に待機しているのであるから。
人為的に、それを冷血な政策として実施しているのは、大イスラエル建設を夢見るイスラエル政府だ。検問所を開き、国連などの第三者機関に活動を許せば、問題は今日にでも片付く。にもかかわらず、ネタニヤフ首相は飢餓発生の報告は嘘だと嘘をつき、ガザ市を陸上部隊で総攻撃、占領する計画を明らかにしている。極右過激主義者のスモトリッチ財政相に至っては、ガザ市への水、電力、その他の供給を断て、と檄(げき)を飛ばしている。彼らは戦争犯罪、人道に対する罪の裁きからもはや逃れられないが、犯罪の上にさらに犯罪を重ねる狂気を演じている。
◆80年近く続く難民生活
母子の写真の背景は、テントだ。少なくともここ2年、暑い日も激寒の日も、そこで暮らさなければならなかったのだろう。そんな運命についても、この母子には何の罪もない。それは、先日、意図的に殺害されたガザ出身で、使命感からアルジャジーラの記者になったアナス・アッシャリーフ氏も同じだ。
外務省でパレスチナ問題を担当していた筆者がガザを初めて訪れたのはオスロ合意後の1990年代半ば、今から30年も前のことだ。当時から、そこにはみじめな暮らしがあるのだろうと想像していたところ、意外に大きな邸宅が並ぶ街並みが現れて驚いた。その一方で、地区内に点在する難民キャンプの生活は当時から悲惨だった。そこには、1947年の最初の「大惨事」以来、現在のイスラエル領内の自宅から、逃げなければ殺される状況の中で着の身着のまま流れ着き、テントを張って暮らし始めた家族がそのまま何十年と住み着いていた。ガザ地区は、昔からの市民と、迷路のような「町」に住む難民が同居する場所で、国連(UNRWA)が、救済に当たっていた。しかし、ここ2年間の戦争で、ガザの住民は分け隔てなくテント生活に追い込まれた。ガザで生まれたアナス記者の家族もイスラエル南部・アシュケロンの出身。実に、80年近くイスラエル国土拡張の被害に遭い続け、ついに殺されたのだ。
◆国家承認の前に救済を
誰の目にも飢餓発生が明らかになって、英仏など欧州諸国はうろたえ、相次いで「パレスチナ国家」を承認する、と言い出した。間もなく開かれる国連総会で、主要国は何万人、何十万人にも及ぶかもしれない餓死者を救わず、存在していない「国家」の承認がふさわしいか否かを議論するとでもいうのか? 首脳が総会に集まる前にまず、人間として最低しなければならないことは、集団虐殺、民族浄化といった、してはならない人道犯罪をやめさせることである。ホロコーストの犠牲者の末裔による新たなホロコーストを許してはならぬ。そのためには、米国抜きで有志連合軍の派遣が必要との意見に筆者は同意する。国連軍を組織するにしても、犯罪の背後に身を隠している米国が拒否権を行使することは間違いないからだ。